-
ブログ・川﨑 依邦
経営再生物語(185)後継者をどうする〈事例A〉
2018年4月6日
〈つぶれる覚悟で〉
①後継者の育成はなるようにしかならない
いくら次の社長になるようにといっても、逃げていく者がいる。とりわけ運送業の経営はドロくさい。人間中心の社会である。首に縄を付けて社長をやらせても向かない者もいる。反対に、社長になりたくてなった者が、いい社長になるとは限らない。「オレは社長だ」と胸を張っているだけでは、乗務員はついてこない。ひとりよがりになる。後継者の育成は、なるようにしかならないと思い定めるべきである。この覚悟があって、次のポイントがある。
②後継者には苦労をさせよ
後継者には苦労がいる。金と人の苦労がいる。この苦労を他人任せにしてはいけない。A社の息子らは経営の苦労をB氏に任せてきた。これでは経営者にはなれない。知識があるからといって経営者になれるわけではない。単なる頭でっかちである。知識を知恵にしていくものが苦労である。金と人の苦労は買わなくてはならない。
③後継者にすべて任せよ
後継者は机上の育成で何とかなるものではない。A社の事例でいえば、2代目はB氏に社長を譲るべきではなかった。ストレートに、例え40歳であろうと、息子に譲るべきであった。B氏の希望通り辞めてもらうことがベターである。少なくとも後継者の育成ということであれば、40歳の息子が社長をやるべきであった。
「それではA社がつぶれる。銀行も荷主も反対する」︱︱それでいいのである。つぶれてもいいから任す。ここのところが、後継者教育のポイント中のポイントである。なるようになる。
後継者教育の難しさは、正解がないところにある。B氏の30年間の歩みは後継者の育成ポイントの奥深さを示している。
この記事へのコメント
-
-
-
-
筆者紹介

川﨑 依邦
経営コンサルタント
早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。
株式会社シーエムオー
http://www.cmo-co.com -
「ブログ・川﨑 依邦」の 月別記事一覧
-
「ブログ・川﨑 依邦」の新着記事
-
物流メルマガ




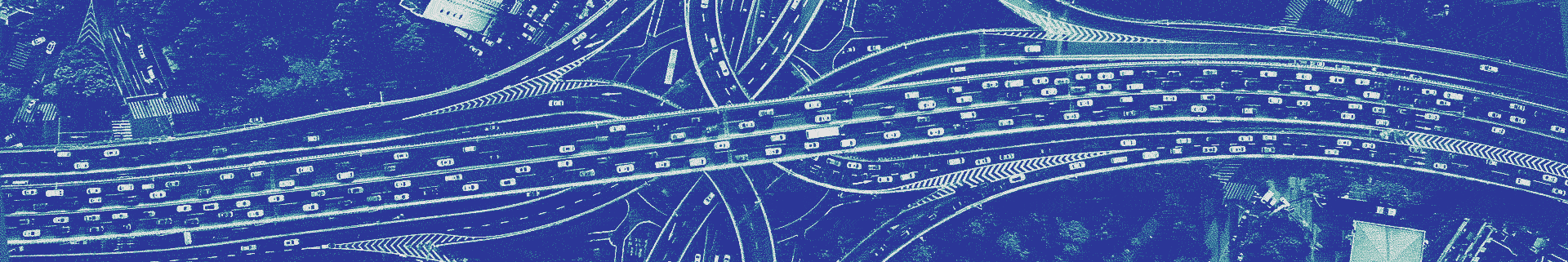


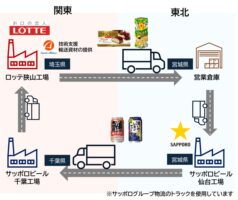




と杉野工場長(右)-e1771058134528-300x193.png)



















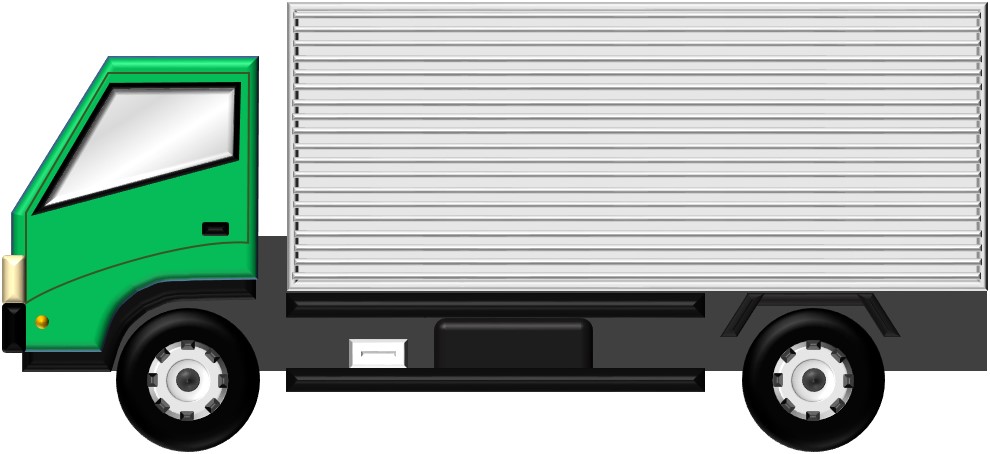



と國安常務。-e1769499382572-500x232.jpg)


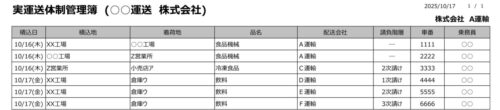


-300x197.jpg)


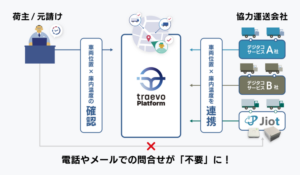




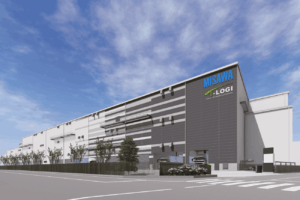





と山田元気取締役-457x500.jpg)




